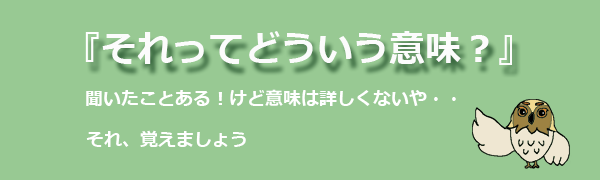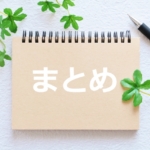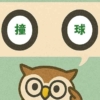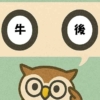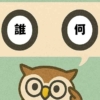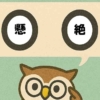「負笈」の意味と読み方とは?ヒントは「背負う」
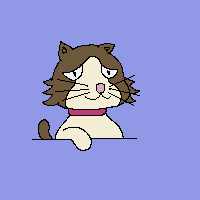
負笈って、なんと読むのかな??
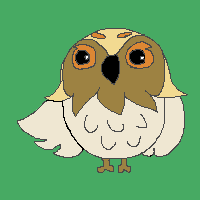
「負笈」はね、「ふきゅう」と読むんだよ。
負笈の意味
《笈 (おい) を負って遠くへ行く意》遠くへ勉学に出かけること。遊学。
出典 デジタル大辞泉(小学館)
負笈はここに注意
「笈」は準1級の漢字のため、間違えないように注意しておきましょう!
言葉の難しさ・・・★★★☆☆
「笈」の読み書きが難しいため。
すぐ忘れてしまいそう?それなら・・・
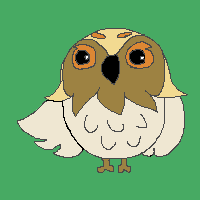
つまり「負笈」の意味は、遠くへ勉学に行くことなんだね。
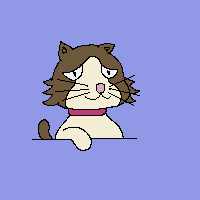
何で勉強・・・?
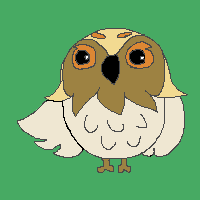
何を背負っているのかを知れば、分かると思うよ。
「負笈」の「負」は他に「ぶ・ふう・負ける・負う・負む・負く」とも読みます。意味は、
- 物を背にのせる。「負笈」など
- うける。こうむる。「負担」など
- 頼みとする。「抱負」など
- 戦いに負ける。「勝負」
- 数学で0より小さい数。「負数」など
- そむく。さからう。
となっています。重い物を背負っているのかも知れませんね。
「笈」は他に「おい」とも読みます。意味は、
- おいばこ。荷物や書物を入れて背負う、竹製の箱のこと。「秘笈」など
となっています。おいばこは、書物を入れて背負うための箱みたいです。
遠くで勉強をするために、書物を入れた箱を背負って行くイメージで「負笈」と覚えてはいかがでしょうか?🎒
「負」の部首は「貝」で、貨幣や財貨などに関する字に主に使われますね。
とてもカンタンな漢字ではありますが、「貝」の上に「ク」のようなものをのせてあげましょう。
背負う人の形からという話や、背を向けることから「負」が成り立ったという話がありますよ。🧐
「笈」は、部首である「竹」の「たけかんむり」に、「及」となっています。
「たけかんむり」は、竹の種類や状態などに関する字に主に使われますね。
「及」は達する、行きわたる、及びという意味があります。
人の背に、追いかけるようにして負われたおいを意味して「笈」が成り立ったという話がありますよ。🧐
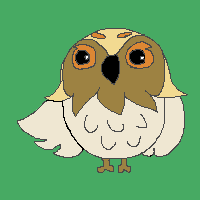
負けているわけではないんだね。

「負笈」の類語
遠くへ学びに行く、という意味の言葉が似ていますね。
- 遊学・・・よその土地などへ行って勉学すること。
- 留学・・・他の土地へ行き、学ぶこと。
同じ読み方の熟語👀
- 不休・・・休まずに活動を続けること。
- 不朽・・・いつまでも価値を失わずに残ること。
- 普及・・・広く行きわたること。
- 腐朽・・・くさって形が崩れること。
- 不急・・・今すぐでなくても良いこと。
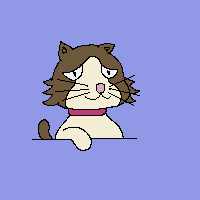
なるほど、書物も入っているんだね。
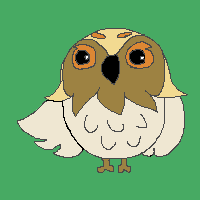
もしかしたら、多くの物を背負っているのかも・・・。
まとめ
「負笈」は、遠くへ勉学に行くことなんですね。
遠くで勉強をするために、書物を入れた箱を背負って行くイメージで覚えてはいかがでしょうか?🎒
「負」の部首は「貝」で、貨幣や財貨などに関する字に主に使われます。
とてもカンタンですが、「貝」の上に「ク」のようなものをのせましょう。
背負う人の形からという話や、背を向けることから成り立ったという話がありますよ。🧐
「笈」は、部首の「竹」の「たけかんむり」に、「及」です。
「たけかんむり」は、竹の種類などに関する字に主に使われますね。
「及」は達する、行きわたる、及びという意味を持ちます。
人の背に、追いかけるようにして負われたおいを意味して成り立ったという話がありますよ。🧐