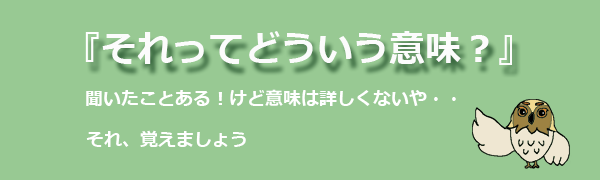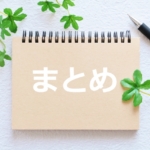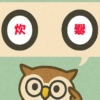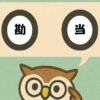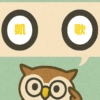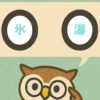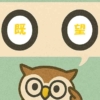「校閲」の意味と読み方とは?ヒントは「調べる」
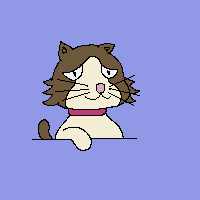
校閲って、なんと読むのかな??
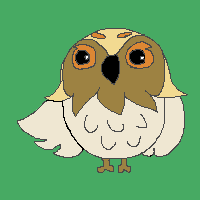
「校閲」はね、「こうえつ」と読むんだよ。
校閲の意味
[名](スル)文書や原稿などの誤りや不備な点を調べ、検討し、訂正したり校正したりすること。「専門家の—を経る」「原稿を—する」
出典 デジタル大辞泉(小学館)
校閲はここに注意
「校」の使い方に、注意しておきましょう!
言葉の難しさ・・・★★☆☆☆
読み書きがカンタンなため。
すぐ忘れてしまいそう?それなら・・・
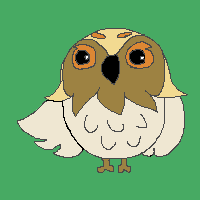
つまり「校閲」の意味は、文書などの誤りや不備を調べて、訂正したりすることなんだね。
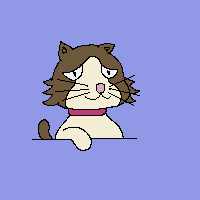
校正とは違うのかな?
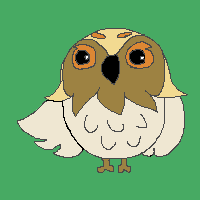
どうやら、チェックする内容に違いがあるようだよ。
「校閲」の「校」は他に「きょう・校べる・校える・かせ・あぜ」とも読みます。意味は、
- まなびや。「学校」など
- 考える。比べる。「讐校」など
- 指揮官。「将校」
- 木を組み合わせたもの。かせ。あぜ。「校倉」
となっています。学校なら、当然考えることは多いですよね。
「閲」は他に「閲する・閲る」とも読みます。意味は、
- けみする。調べる。「検閲」など
- 過ごす。経過する。「閲歴」など
- いえがら。
となっています。調べる他に、経過する意味もあるようですよ。
見ていておかしいなと思うところを調べて考え、時間がある程度かかっても良いので訂正しようとするイメージで「校閲」と覚えておきましょう!🧐
「校」は部首である「木」に、「交」となっています。
「交」は混ざったり、やり取りするなどの意味を持っていますよね。
「交」の方は、人が足を組んでいる象形でもあるようです。
木でできたものが足に交わり、足を組むようにして動けなくなっている。
そこから、かせなどを意味して「校」が成り立ったという話もありますよ。🧐
「閲」は部首である「門」の「もんがまえ」に、「兌」の旧字となっています。
部首の「もんがまえ」は、門や出入り口などに関する字に主に使われますね。
「兌」の旧字は、交換することや楽しむこと、抜け道などの意味を持つそうです。
門を通して見ることを意味して、「閲」が成り立ったという話がありますよ。💂
もし抜け道があったとしても、正規のルートよりは時間が経過してしまいそうですよね。
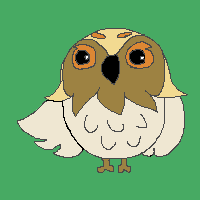
大事な作業だよね。
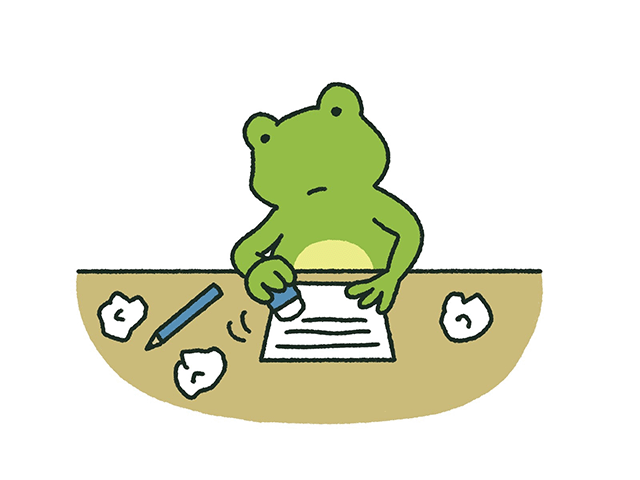
この言葉、どう使う?
- 記事の校閲を担当しております。
- 校閲が行われ、校了した。
- 今回の校閲者は、いつもよりも多くしておいたよ。
「校閲」の類語
書物などを修正する、という意味の言葉が似ていますね。
- 校合・・・2種類以上の写本などを比べて、本文の誤りを正したりすること。
- 修訂・・・書物などの間違いを正し、欠けた所を補うこと。
- 勘校・・・比べて誤りを正すこと。
同じ読み方の熟語👀
- 高閲・・・相手が文書に目を通したり、調べたりすることを敬っていう語。
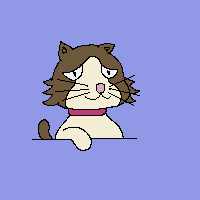
作者も、考えて書いているとは思うんだけど・・・。
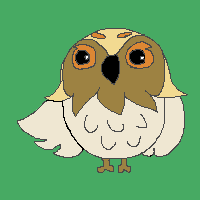
それでも間違いはあるし、勘違いも起こるからね。
まとめ
「校閲」は文書などの誤りや不備を調べて、訂正したりすることなんですね。
見ていておかしいなと思うところを調べて考え、時間がある程度かかっても良いので訂正しようとするイメージで覚えておきましょう!🧐
「校」は部首の「木」に、「交」です。
「交」は混ざる、やり取りするなどの意味を持ちますね。
「交」は、人が足を組んでいる象形でもあるとのこと。
木でできたものが足に交わり、足を組むようにして動けなくなっていることから、かせなどを意味して成り立った、という話もあります。🧐
「閲」は部首の「門」の「もんがまえ」に、「兌」の旧字です。
部首の「もんがまえ」は、門や出入り口などに関する字に主に使われますよ。
「兌」の旧字は交換する、楽しむ、抜け道などの意味を持つとのこと。
門を通して見ることを意味して成り立った、という話がありますよ。💂
もし抜け道があっても、正規のルートよりは時間が経過してしまいそうですね。
こちらはいかがでしょうか?
「聞いたことがあるから、この表現なら大丈夫だろう」
「この表現、かっこいいから使いたいな」
そう思っていたもの、もしかしたら間違えた表現かも知れませんよ。
こちらの本は、現役の校閲者さんが間違えやすい表記や表現を教えてくれます。
自分だけで書いていると、気づかぬまま間違っていることを書いてしまうかも知れませんからね、少しでも間違いを減らしたいものです。
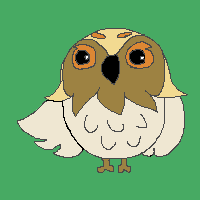
「聞いたことがある!」ということでも、全てを信じないようにしよう。